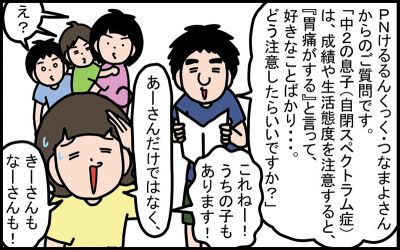新城和博
2019年6月6日更新
スケッチ 第一牧志公設市場の記憶について|新城和博のコラム
ごく私的な歳時記Vol.61|首里に引っ越して20年。「ボーダーインク」編集者でライターの新城和博さんが、この20年も振り返りながら、季節の出来事や県産本の話題をつづります。


スケッチ
第一牧志公設市場の記憶について
那覇の第一牧志公設市場が6月16日をもって現在の建物が閉鎖されて移転する。3年後同じ場所で再建されて戻ってくる。以下、3年後の記憶のためのスケッチ。登場する「男」はぼくかもしれないし、市場ですれ違うだれかかもしれない
エスカレーターが市場の2階へと彼女を運んでいった。
男は手にしていたコラムマガジンを少しもちあげ、合図を送った。
カメラを構えていた彼女は、遠ざかる男の姿を、市場の1階の背景とともに、少しひいたアングルでとらえた。すぱやく何枚かシャッターを切る。
男は周囲を肉屋に囲まれた一角で、彼女がエスカレーターでのぼりきる姿を確認した。
少しして南側の階段から下りてきた彼女は、いい感じで撮れてますよと、デジタルカメラのファィンダーを男に見せた。彼女の職業は新聞記者である。取り壊される公設市場の思い出を取材している。原稿の締め切りはすこし先である。市場が閉鎖される前にその記事は掲載される予定だ。
2階まで吹き抜け構造の公設市場のエスカレーターは、建物の築年数相応の少し古びた姿をしているが、なんの支障もなく稼働していた。
どうして下りのエスカレーターはないんでしょうね。彼女の疑問に、男は笑った。建物の北側にはエレベーターもあるのだが、とても小さくほとんど目立たない場所にある。したがってほとんどの客は、エスカレーターで上がって階段で下りてくる。
男はこの市場界隈(かいわい)の育ちで、47年前、建物が新築されたときのことも覚えている。小学生だった彼は、母親に連れられて市場の買い物にいくことは日々の暮らしの中にあった。
それまでの市場は、古い木造のうす暗いイメージで、あとで知ったことだが、廃材を使って建てられた、戦後の混乱とバイタリティーをまとった建物であった。そのうす暗さのなかに並べられているたくさんの豚肉が、ときおり男の記憶によみがえる。それはもしかして夢のなかの光景ではなかったのか、と男はじぶんの記憶に疑問を持っていた。
しかし生まれ育った街のたたずまいに関心を持つような歳になり、ふと手にしたアメリカ統治下時代の風景をまとめた写真集の中からかつての市場の写真をみつけ、現実の風景であることを確認した。あのうす暗さは確かに市場だった。
夢でなかったよ、と男は彼女の質問に答えた。
出来た当時の公設市場の印象はどうでしたか、と彼女は取材ノートを開く。
新しく出来た公設市場のなかはぴかぴかとしていた。小さくコマ割りされた店舗の前に冷蔵展示された肉や魚、明るい照明、中央が吹き抜けとなった開放的な構造とエスカレーター。小学生のころから、市場の活気のあるざわめきの心地よさを求めて、市場内を歩いていた。それは高校、大学、そして仕事をはじめて今に至るまで同じであることに、男は気づいている。
そういえば、中学生のころ、愛用のラジカセをもって、市場の音を録音したことがあった。雑踏の雰囲気を録りたかったんだろう。いまそのカセットテープがあればよかったな。
そのような話をとりとめもなくしながら、しばらく取材は続いた。2階の食堂で食事でもしながら、もう少し話をしようということになり、あらためて2人はエスカレーターにつれられて、2階へと上っていく。のぼりきって正面の食堂は、呼び込みの声と観光客のざわめきが響いている。いつも通りだが、その光景は市場にとっては新しい姿でもあることを、男はある種の感慨をもって眺めた。もうすぐこの光景は姿を消すのだから。

長くこの街にいる男は、あるきながら見える街角の風景を、何層にもわたる記憶の重なりとして認識している。いま目にする風景は実は薄皮のようなもので、少しふれれば新しい皮がめくれ、古い記憶が現れる。街の風景が更新されるたびに、古い記憶は消えていくように思われたが、そうではなかった。同じ場所に沈殿されているのだ。この街にいる限り、どんな橋を渡ろうとも、いとも簡単に、あの薄暗い建物のなかで豚肉が並んでいる場所にたどり着くことができるのだ。1ヵ月後、この建物に男は入ることができなくなる。
この記事のキュレーター
- キュレーター
- 新城和博
これまでに書いた記事:104
ライター/編集者
1963年生まれ、那覇市出身。沖縄の出版社「ボーダーインク」で編集者として数多くの出版物に携わるほか、作詞なども手掛ける。自称「シマーコラムニスト」として、沖縄にまつわるあれこれを書きつづり、著書に「うちあたいの日々」「<太陽雨>の降る街で」「ンバンパッ!おきなわ白書」「道ゆらり」「うっちん党宣言」「僕の沖縄<復帰後>史」などがある。